前回の記事では、代表・俣野泰佑さんの原体験に迫りながら、掲げる理念「毎日をW杯に」に込めた想いや、株式会社スポカレが描く未来像を紐解いた。「スポーツを、もっとおもしろく」。その想いの根底には、スポーツを愛し、誰かの“好き”に本気で向き合う社員たちの存在がある。後編では、“全員をプロデューサーに育てる”というユニークな組織づくりに注目。俣野さんの言葉を借りれば「変わり者」集団が躍動し、チームで支え合いながら成長していく環境、そして“推し”という感情が新たな経済価値を生む可能性について、現場で起きているリアルなエピソードから紐解いていく。
(取材・執筆:伊藤 千梅、編集:伊藤知裕、池田 翔太郎)
――改めて、スポカレの強みとはどんな点にあるとお考えですか?
中長期のプロジェクトが多いことです。3年以上ご一緒しているスポーツチームやリーグのクライアントが大半で、制作会社というより、プロジェクトチームとして伴走している感覚に近いですね。
あとは担当領域が広いことも強みです。単発の案件でできることは限られているなかで、小さなことを大切にしていくことで「さらにここも」「ここもいけるか」とたくさん任せていただくことも多くあります。SNS運用からスタートした案件が、いつの間にかWebや広報、マーケティングまで幅広く任せていただけるようになることも珍しくありません。多くの範囲を任せてもらっているからこそ、様々なチャネルの施策が連動し、相乗効果が出せることも特徴だと思います。

――担う領域が広がるにつれて、チームの人数も増えていくのでしょうか?
クライアントごとに「ディレクター」がいて、基本的には窓口として全てを管掌します。ただ、その人がすべてを担うわけではありません。背後には、分野ごとのエキスパートがいるチーム体制があって、一人のディレクターが“ハブ”となりながら、複数のプロジェクトを進めていく仕組みです。
――1人で全部を背負うのではなく、チームで仕事をしていくのですね。
そうですね。仲間の力を借りながら、助け合って進めていくのがスポカレのスタイルです。
たとえば入社1年目の社員で、SNS運用には強みがあったものの、Web制作の知識はほぼゼロというケースがありました。でも、社内のWeb担当とペアで動くことで、実務を通じて少しずつ理解を深めていき、今ではSNSもWebも一定レベルでこなせるようになっています。背後に支えてくれる仲間がいることで、未経験の分野にも安心して踏み出せるし、それが成長の加速にもつながっていると感じています。
――個人のビジネススキルアップに最適な環境ですね。
マニュアルや研修などの育成手段もありますが、やっぱり一番早く、確実に力がつくのは「実際に仕事をすること」だと思っています。そうでないと、本当の意味で身につかないんですよ。
もちろん、最初から全部ひとりでこなせる人はいません。だからこそ、最初はチームでカバーする。クライアントにはしっかりとしたアウトプットを提供しながら、本人は安心してチャレンジできる。チームの力を借りることで、個人の10倍くらいの成果を出せるんじゃないかなと思います。
――10倍……!
あくまで感覚ではありますが、それくらいを目指したいなと思っています。たとえば、自分ひとりでは処理できない業務も、まわりに頼れるエキスパートがいれば任せることができる。そうして“10倍のアウトプット”を出し続けていると、不思議と自分の実力も追いついていくんですよ。少しだけ背伸びをしていくことで、自然とその基準に手が届くようになる環境が、うちにはあると思っています。
――確かに、常に一歩先を追いかける感覚ですね。
はい。ただ、個人プレーで動いている会社では「背伸び=プレッシャー」になってしまうケースもあると思います。
たとえば営業会社で、社員や同期がライバルというような会社では、なかなか相談できる人が社内にいない場合もあると思うのですが、弊社には各分野で相談できるエキスパート=仲間がいるので、社内で色々なことを吸収して、自然体で成長していけると思います。
――成長した先に、どんな人材になってほしいと考えていますか?
僕は社員を全員「プロデューサー」にしたいと考えています。
プロデューサーには2つの意味があると思っていて、一つは物事を前に進める、つまり生み出す=Produceすること。もうひとつは、世間一般的なプロデューサーのイメージで、人・物・金・質・量・スピードといった仕事の要素を、俯瞰してマネージングできること。社員全員をプロデューサーにすることが組織としての目標であり、経営者としての僕の目標の一つです。

――どのようにして、プロデューサーになっていくのでしょうか?
能力的な成長ももちろん重要なのですが、まずベースとして重要なのは、「人に貢献したい」という気持ちです。
たとえば、クライアントの成功を心から願っていれば、「こんなことも一緒にやりたい」「これも提案したい」という気持ちが自然と湧いてきます。クライアントの目指す世界に共感できれば、伴走して一緒に前に進んでいける。結局、究極的には「良いヤツ」だったらプロジェクトはうまくいくと思っています(笑)。
もちろん、最初からすべてができる必要はありません。むしろ、何からやればいいかわからないのが普通。できることを一つずつ増やしながら、「自分はこのプロジェクトにちゃんと貢献できた」という確証を、それぞれが積み重ねていけば、気づけばプロデューサーとして成長していると思います。
――だからこそ、未経験や異業種出身の方も活躍できるんですね。
うちは“エキスパート”は集めていますが、“プロフェッショナル”を集めているわけではありません。何かひとつ強みはあるけど、それ以外はまだまだという、いわば「変わり者」の集まり。でも、三角や四角のような多様な形をした人たちを集めて、全体として丸く機能するようなチームをつくっているイメージです。
そんなチームの中で、自分の持ち味を活かしながら、他のメンバーから刺激やスキルをもらっていく。自分ひとりでは出せない10倍のクオリティをチームで出していくうちに、自然と自分自身の総合力も高まっていく。そんな環境が、スポカレにはあると思っています。
――改めて、スポカレにはどんな人が向いていると考えていますか?
すべてを一人で完結できる人なんて、世の中にはほとんどいません。だからこそ「ごめん」「できない」「助けて」と言えることが大事だと思っています。ただこれは、意外と難しいことでもある。つまり、自分にできないことを認める“謙虚さ”が求められます。
うちの会社では、素直に「できない」と言える人ほど成長します。逆に、それを言わずに自分だけでなんとかしようとする人ほど、キャパの範囲内でしか動けず、成長のスピードも遅くなってしまう印象があります。
――前回も「挨拶をすること」「間違ったら謝ること」根本的なことを大事にしているとおっしゃっていました。
僕は採用のときにも、その人が周囲にとって“良いヤツ”であれるかどうかは大切にしています。普段から誰かのために行動できる人は、困ったときに自然と「大丈夫?」と声をかけてもらえる。挨拶も実はつながっていて、決して体育会系っぽい文脈の「挨拶」とか「朝礼」とかが重要なのではなく。挨拶がちゃんとできる人は、相手を少しでも笑顔にしたいとか、周囲に気を配りたいという気持ちがある。その姿勢や心意気が大切だと思っています。
「ありがとう」と言わなくても仕事は成立しますが、その一言を言える人のほうが、あとで助けてもらえるし、関係性もスムーズになります。だからこそ、僕にとって「挨拶ができるかどうか」は、“いいやつかどうか”を見極める一つの指標なんです。
――人を喜ばせたいという「他喜力」みたいなものでしょうか?
そうですね。たとえば、目標に届かなかったときに、自分のことだけじゃなく「クライアントに申し訳なかった」「チームに迷惑をかけてしまった」と感じられる人は、きっと大きく成長すると思います。うちのメンバーには、そうした捉え方ができる人が多いですし、そういう感覚をもった人を採用するようにしています。
あとは「他人軸」で生きている人のほうが、スポカレの雰囲気的には合うかもしれません。そもそも仕事ではクライアントに貢献しないといけないし、そのなかで、たくさんの社内の人たちの力も借りないといけない。
そういった面では、ある意味「推し活」は一つの能力だと考えています。

――「推し活」ですか?
はい。いかに他人を推すかが、この仕事の勝負だと思うので。推し力が高い人は自然と周りへの貢献ができますし、クライアントを“推す”のもうまいです。すぐに貢献したいというマインドになりますし、どうすれば喜んでもらえるかを常に考えている。共感力が高いことが能力の一つだと思います。なので、社内でも「推し活」を許容する雰囲気を大切にしています。みんなそれぞれ好みは違いますが、「またあの人ライブに行くらしいよ」とか「海外の試合観戦に行くんだって」といった話も、自由に話せる環境にしています。
――自分の推し活が、肯定される会社なのですね。
推しがある人って、人生のエネルギーの7~8割をそっちに注いでいると思うんですよ。残った2割で仕事しても、時間もエネルギーももったいないじゃないですか。だったら、その2割の仕事も“好き”を活かせる状態をつくっていきたいと考えています。
実際に、K-POP好きの社員を採用したら、韓国アイドルに関連する仕事が舞い込んできたこともありました(笑)。いわゆる「引き寄せの法則」ってあると思うんです。僕自身も、社員の好きを活かしたいと思いながら仕事をしているので、それがそういう現象につながっているのかもしれません。
▼メンバーのインタビューはコチラ
――いつから今のような「チームで取り組む」会社になったのでしょうか?
創業は2018年で、今年で8年目になります。立ち上げたばかりの頃は、搾取じゃないですけど、社員の頑張りに依存したというか。数字ばかりに目を向けていて、正直、社員一人ひとりのことをきちんと見られていなかったと思います。
ただ、それではうまくいかない。そう気づいてからは、「この人はどう生きたいのか」「この会社と一緒に、どんな未来をつくりたいのか」と社員の人生と会社が交差するところに、化学反応が起こるのではないかと考えるようになり、徐々に組織の形も変わっていきました。

――「チームでやる」という選択肢に、もどかしさはありませんでしたか?
もちろん、プロフェッショナルばかりを集めた方が理論的には出力が上がるのですが、実際の組織はそれではうまくいきません。
色々な組織や会社を見ても、専門性の高い人材を集めれば成果が出る、という単純なものではない。むしろ、自分の得意・不得意を理解して、素直に連携しようとする人たちが集まる方が、結果的にアウトプットの質が高くなる。そういった現場を、これまで何度も見てきました。
――では、これからはどんな会社でありたいと思いますか?
選手やチーム、スポーツファンを支える会社であることは、もちろん変わりません。ただそのためにも、まずは自分たちのメンバーを大切にしたいと思っています。
社員一人ひとりが、自分の「好き」や「推し」を大事にしながら、安心して挑戦できること。その背中を会社としてしっかり支えることが、やがてクライアントやファンに還元されていく。そんな循環を生む“良いチーム”でありたいですね。「誰かを支えることが、誰かの推しになる」スポカレはこれからも、そんな組織を目指していきます。
▼スポカレの求人を見る▼
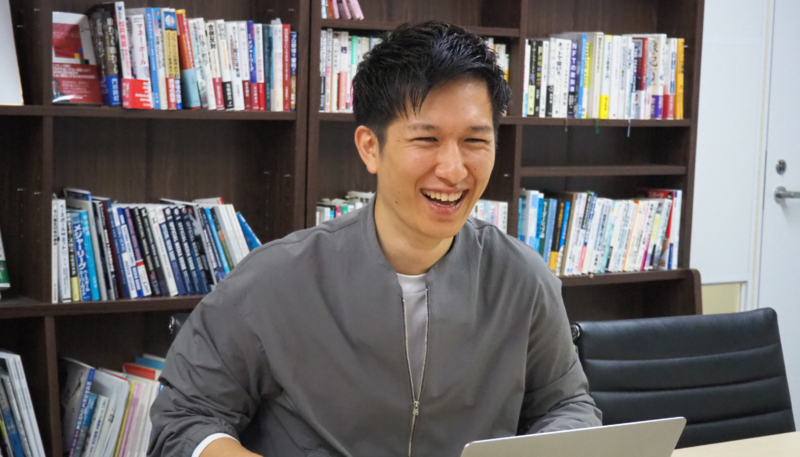
【PROFILE】
俣野 泰佑(またの たいすけ)
株式会社スポカレ代表取締役社長。東京大学在学中はサッカー部に所属し、学生GMを務める。都学連の運営や学生団体の運営なども兼任。スポーツとビジネスを結びつける原体験を得たことをきっかけに、2018年に株式会社スポカレの立ち上げに参画。スポーツ観戦の価値向上とデジタルを活用したマーケティング支援事業を展開している。現在は自社プロダクト「スポカレ」の運営と、スポーツリーグ・クラブへの集客支援の両軸で事業を推進している。
| 設立年月 | 2018年06月 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 俣野泰佑 | |
| 従業員数 | 43名(パート/アルバイト含む、2023年10月時点) | |
| 業務内容 | ||
友達追加するとあなたに合ったスポーツ業界情報をおしらせできます
 友達追加する!
友達追加する!